なぜ会社にITシステムが合わないのか?
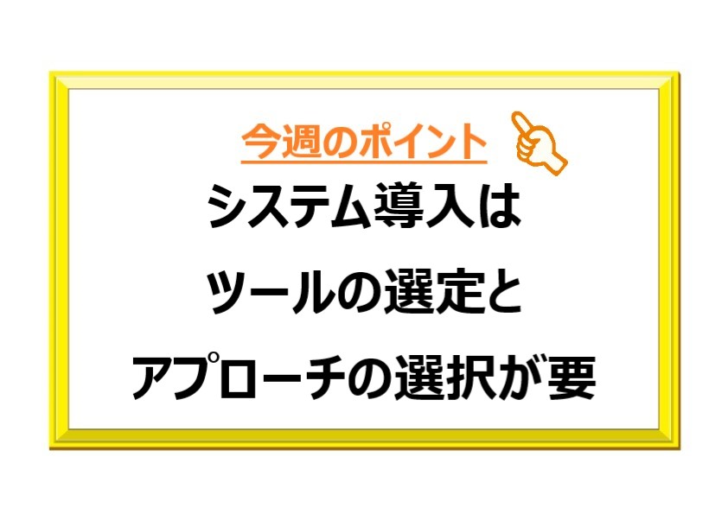
■システムが使われない理由
業務プロセスの改善のご支援させていただいているクライアントから、「うちの会社は、自分たちの仕事を変えようとしないのでシステムが使われないんですよ・・・」とのこと。今回のご支援はシステム導入ではないのですが、非常に良くあるお話でしたので、コラムに取り上げてみました。
実は、システム導入の失敗の多くが、「会社の業務」に「システム」を無理に合わせようとするために起こります。このようなケースでは、従業員は自分たちの会社にシステムが合わないということで、そのシステムが使えないと考えてしまいます。結果として、システムが使われにない状態が続いてしまうのです。
■トップダウン型とボトムアップ型のシステム導入
システム導入には、ボトムアップ型とトップダウン型の2つがあります。
ボトムアップ型
ボトムアップ型のアプローチとは、会社の業務に合わせてシステムを作っていくことです。スクラッチ型のシステム開発というのは、会社の業務に合わせてシステムを設計・開発することなので、ボトムアップ型のアプローチの典型です。
ボトムアップ型のアプローチのメリットは、会社の業務に合わせてシステムを作れることです。従業員からすると、自分たちの仕事のやり方を大きく変える必要がないため、システムを受けれやすいです。
一方でデメリットは、システム開発にかかる時間や費用が大きくなるという点です。
トップダウン型
トップダウン型とは、システムが持っている標準機能を活用したシステム導入の手法です。会社の業務をシステムの標準機能に合わせて変えていくことが求められます。パッケージソフトとは、この標準機能を持っているシステムのことで、トップダウン型のアプローチに当てはまります。
トップダウン型のアプローチのデメリットは、会社の業務にシステムが合わない可能性があるという点です。
一方でメリットは、比較的にシステム開発の時間や費用を抑えることが出来るということです。また、標準機能に合わせて、会社の業務を改善していくことも可能です。
■基本はトップダウン型を選ぶ
さて、ここで冒頭のクライアントの言葉に戻ってみましょう。
実は、クライアント企業は、パッケージソフトを導入しています。つまり、トップダウン型のアプローチが適しているケースであると言えます。しかし、従業員は、自分たちの業務に合わせるべきだというボトムアップ型のアプローチの発想でシステム導入を進めてしまっていたのです。そのために、「自分たちの仕事にあわなくて使えない」という意見が出てきてしまうのです。
特に中小企業において、システム導入を進める場合には、多くの場合、ボトムアップ型のアプローチは適していません。なぜなら、システム開発のコストや時間がかかりすぎてしまうからです。ですから、基本はトップダウン型のアプローチを選択することが正しい場合が多いです。
では、どのすれば、トップダウン型のシステム導入を成功させることができるのでしょうか。それには、システム導入を開始する前に、トップダウン型のアプローチを採用するのだという意識を会社の中に広めることが重要です。そのためには、会社のトップの意識から変えていくことが大切となります。
そして、会社の目指す方向性からIT戦略へと落とし込むことが求められます。つまり、会社が進むべき方向性を描き、そのために、どのように会社を変えていこうとしているのかを明らかにし、それに適合したシステムを選定してくことが極めて重要です。
間違っても、他の会社もシステムを入れているし、このシステムを入れれば生産性が上がりそうだというような発想でシステム導入を進めないようにしてください。ぜひ、会社の進むべき方向に邁進していくためのシステムの活用を現実のものとしてください。
(第59回: 2019/11/27)
